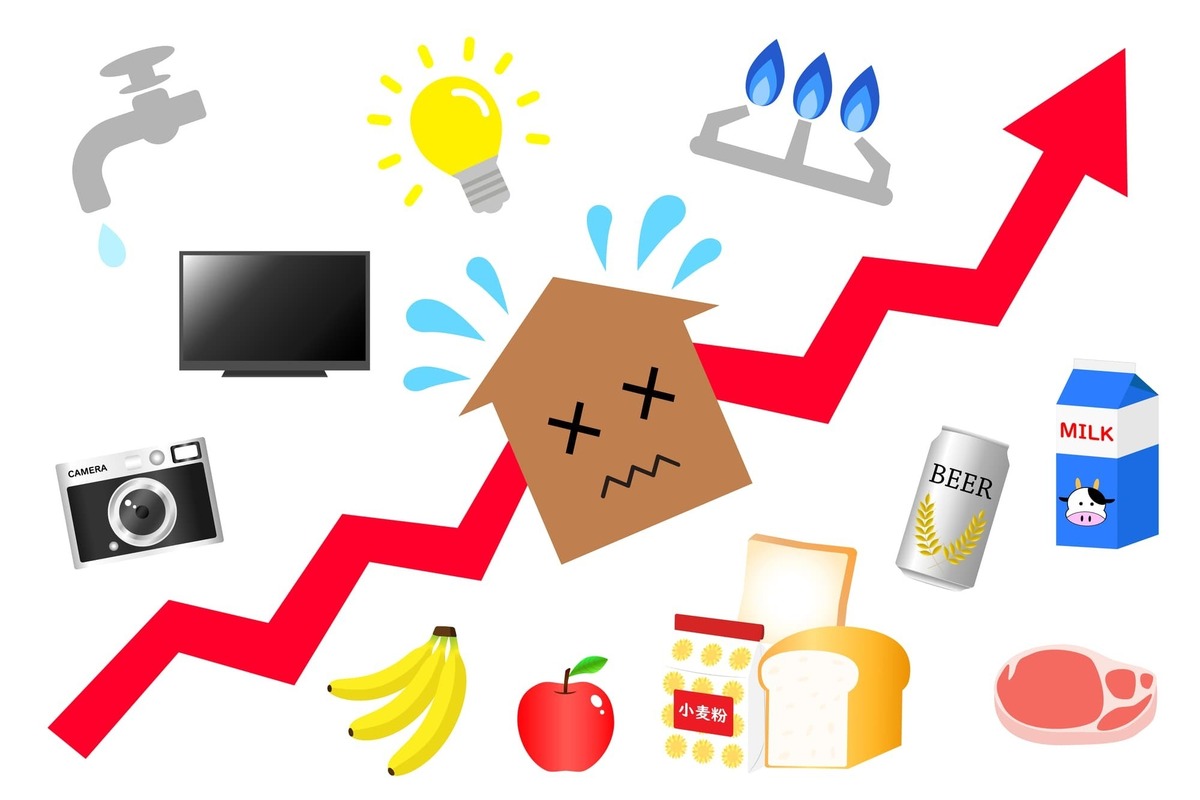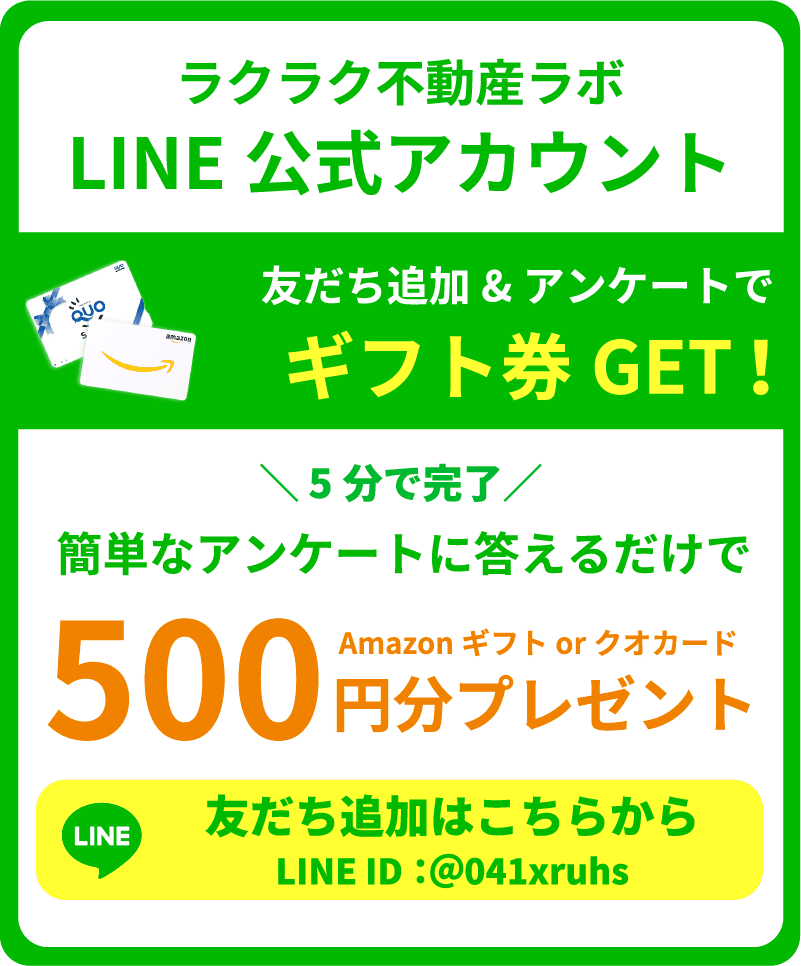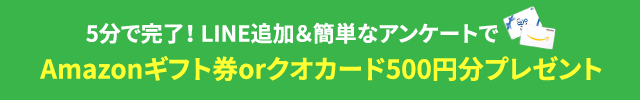最近、スーパーでの会計や電気代の明細を見て「前より高くなった」と感じる方は多いはずです。数字上は同じお金を持っていても、買える量が減っていく——これが物価上昇(インフレ)の怖さです。
では、なぜ物価は上がり、私たちの“貯めたお金”にどんな影響があるのでしょうか。本コラムでは、物価上昇の仕組みをやさしく整理したうえで、物価に強い“貯蓄の置き場所”を考えていきます。
預金は安全だがインフレに弱い
物価上昇の背景は一つではありません。代表的には次の三つがあります。
①需要と供給の不均衡:景気回復や人口集中で「買いたい人」が増える一方、生産や物流が追いつかなければ価格は上がります。
②コストプッシュ:原材料やエネルギー、人件費など“作る側のコスト”が上がれば、商品・サービスの価格転嫁が進みます。
③マネー環境の変化:金利やお金の供給量が緩むと消費・投資が活発化し、物価を押し上げます。
要するに、需要が強い・供給が細い・お金が回る——このどれか、もしくは複合で物価はじわじわ上がるのです。
銀行預金は元本が減らない安心感があります。ただし、名目額は減らなくても“買える量”は減り得るのがポイントです。たとえば100万円を預け続け、10年で物価が2割上がれば、同じ100万円で買えるものは実質80万円分に目減りします。低金利のまま物価だけが上がると、預金は静かに細っていくのです。
大切になる“物価連動の貯蓄”
ここで大切なのは「預金をやめる」ではなく、「目的別に置き場所を分ける」という考え方です。日々の予備資金は流動性の高い預金へ、将来の購買力を守る分は物価に強い資産へ。この住み分けがこれからの家計防衛の基本線になります。
マンション投資では単なる値上がり期待だけではなく、家賃という継続収入が得られる点が特長です。家賃は相場に連動するため、賃貸市場は地域需給や物価の影響を受けやすく、長期では家賃水準が見直される局面が訪れます。土地・建物といった“形がある”資産は、貨幣価値の変動に対し相対的に強い側面があります。
“守りながら増やす”設計ができるのが不動産の強みです。ポイントは、安全資産だけに偏らないこと。インフレが続く環境では、「増やす」よりも先に“減らさない”設計が効いてきます。物価に強い資産を取り入れ、預金の弱点を補う——それがこれからのスタンダードになっていくはずです。
まとめ
物価が上がる背景は、需要・供給・マネーの三つ巴。預金は“見た目は減らない”ものの、物価上昇下では実質価値が減る弱点があります。そこで、物価とともに価値や収益が動く資産を家計に混ぜることが重要です。なかでも不動産は、家賃というインカムと現物資産としての安定感を併せ持つ、有力な“物価連動の置き場所”になり得ます。「預けるだけ」から「置き場所を設計する」へ。あなたの家計も、今日からアップデートしてみませんか?
ラクサスマネジメントでは、お客様のライフプランに合わせて、最適な資産形成のご提案を行っています。ぜひお気軽にご相談ください。
ラクサスマネジメント株式会社
ライフコンサルティング事業部
飯島陸

北海道出身。
社長のインタビュー動画を拝見して社名に込められた意味と熱量に惹かれたことと、実力主義の環境で成長していきたいと考えたため、入社を決意。
休日は映画館や美術館に行ったり、料理をして過ごしている。
関わるすべての人に愛される人間になることが目標。
前職において業務委託の個人営業としてアポイントメントセールスに携わっていた経験を活かし、日々真剣に営業活動に取り組んでいる。